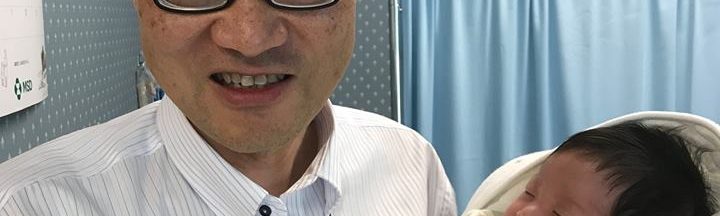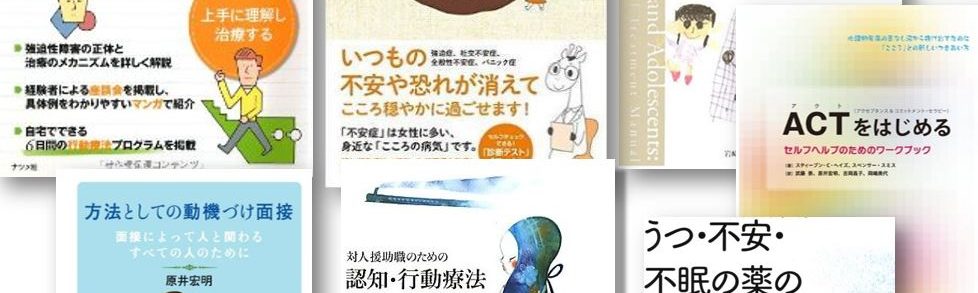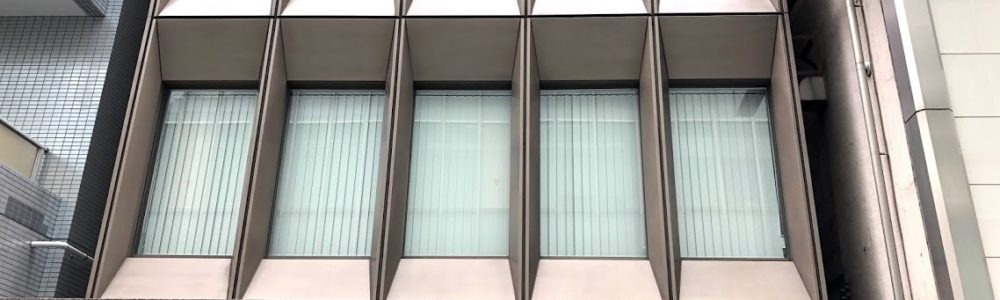不安障害の認知/行動療法 心身医学 51(12), 1071-1078, 2011-12-01
[1]はPavlovの発想を広げ,「皮質内蔵生理学」を提案した。彼はベルや図形のような外部からの刺激だけでなく,体で感じる温度や胃腸の膨らみのような内部感覚も条件刺激になること,嘔吐や下痢のような消化管の運動も条件反応になることを示した。管を通して薬物を胃腸に流すと同時に室温を上げることをすれば,腸の運動を室温に条件づけすることもできる。他にも特定の食物の味覚とその後の不快な情動は容易に結びつくことが知られている。1回だけの恣意的な学習で味の好き嫌いができ,これはGaricia効果と呼ばれる[2]。一方,被験者はどんな薬物が胃腸に流されているか,室温がどう変わったか,微妙な味の変化をすぐには意識できないから,無意識に支配されて腸が動いている,ストレスで下痢を起こしたとか考えるようになる。このような恣意的な理由づけ行動も現代学習理論で説明ができる。人間は理由づけが好きであり,それで安心する。そして自分で作った理由づけに縛られる。
現代古典的条件づけ理論は,Pavlovの条件性制止を隠蔽や阻止,条件性抑制に分けて扱うようになった。現代理論の応用の1つが,抗がん剤治療の場面にプレ・エクスポージャーすることである。抗がん剤治療を行うと,必然的に嘔吐(無条件反応)を伴う。これを繰り返す内に点滴ボトル(条件刺激)をみるだけでも悪心(条件反応)が生じるようになる。隠蔽や阻止を上手に使えば悪心反応の成立を未然に防ぐことができる[3]。
このようにPavlovの実験神経症から始まったCBTは,現代では1つの治療法と呼ぶのがふさわしくないほど,種々あちこちに広まり,使われるようになった。これには種々の理由がある。
- 1980年代にDSM-III[4]が神経症概念を解体し,不安障害と身体表現性障害,解離性障害に分けてしまった。CBTのライバルである精神分析にとって重要な疾病概念であったヒステリーが解離性障害と転換性障害に分けられ,病名自体がなくなってしまった。不安神経症はパニック障害と全般性不安障害に分けられた。この結果,精神分析が持っていた伝統的な疾患説明概念が使えなくなってしまった。一方,CBTは不安障害などを説明する概念として「認知モデル」を持っていた。新しい診断基準が生じるたびに,新しい疾患説明概念を産出できるという融通無碍なところがCBTにはある。
- CBTは最初から,実験を行う伝統があった。全ての治療手続きをマニュアルにまとめて,そのマニュアルに添って治療を行った群と,そうではない群を比較する平行群間試験が最初から行われていた。エビデンスに基づく医療(Evidence Based Medicine,以下EBM)の普及も同時に起こった。EBMを行うことが,すなわちCBTを行うことになった。伝統的な精神分析などの他の精神療法はCBTをマニュアルに頼りすぎる,,表面的だ,個人を集団に還元している,などと批判しているうちに,EBMの時代に取り残されてしまった。
- 新しい疾患説明概念や理論に対するハードルが低いので,論文を出しやすい。
CBTが広汎に拡がった現在でも,最初に2つあげた特徴は今でも変わらない。一方,#2 「実証的・実験的証拠に基づくことのみ主張する」についてはあやふやになってきている。拡げることに重点が置かれすぎて,拡げた結果がどうなったかについての検討はまだこれからだと言える。臨床場面でも,精神分析と競い合っていたころには当然だった機能分析がおろそかにされがちになった。このころは1人1人のケースが実験場面であり,モデルは作業仮説に過ぎなかった。治療は仮説を確かめるための実験だったのである。今日では,できあいの認知モデルを患者に当てはめ,マニュアル通りに治療を進めることがCBTを実践することになってしまった。これらはDSMやEBMに向けられた批判と同じである[5]。
それでもCBTは広まるしかない。誤解も同時に広まる。最初に,良くある質問・誤解を取り上げ,答えるようにしよう。
CBTについてのQ&A
認知療法と認知行動療法,行動療法,行動分析はどう違うのか?
治療者や研究者個々人の違いと比べたら,たいした違いはない。この違いは政党名に似ている。それぞれの名称には歴史的経緯がある。社会党を例に挙げてみよう。民主社会党や民社党,民主党,社会民主党などさまざまに分かれ,名称を変え,最後は,社会党という名称自体が消えてしまった。同じ社会党に所属していても個々人にはそれぞれの異なった主張があり,その主張は別の政党のものと同一だったりしていた。今日,日本には行動療法学会と認知療法学会,行動分析学会があるが,著者自身はこれらの3つの学会と関係がある。どの学会のどんな場面にいるかに合わせて,認知療法・認知行動療法・行動療法・行動分析の名称を使い分けている。CBTで大事なのは,名称や概念の違いではなく,現実の場面でどう行動し,どういう結果を出しているかである。
認知を変えなければ行動は変わらないのか?
認知と行動の関係はダイナミックである。どちらが後先ということはない。行動を変えなければ認知が変わらないこともある。もし,認知を変えようとして悪戦苦闘し,1人で考え続けているならば,行動を変える方を先にしたほうが良い。逆に,行動を変えようとして,いろいろな行動的技法を試し,それでも行動を変えられないでいるのならば,その行動についてどう考えているのか,どのような価値を感じるのかについて患者と治療者が話し合う必要がある。
どんな疾患や症状に適応があるか?
どんな疾患や症状にでも,が答えである。CBT自体は融通無碍だからである。しかし,EBMの目から見れば,CBTと他の治療,無治療と比較した場合にCBTにアドバンテージがあるかどうか,そして現実的な目から見れば,その疾患や症状にCBTを行って治療実績をあげている治療者がいるかどうか,による。たとえば,うつ病やパニック障害の場合はCBTではないプラセボ心理療法(グループミーティングや暗示),薬物療法などでもかなりの治療効果がある。社交不安障害の場合,CBTと薬物療法の治療成績を比べたときCBTは優位とは言えない[6]。EBMの目からみて,他の治療法よりもはっきりとしたアドバンテージがあるのは,不安障害の中では強迫性障害と特定の恐怖症である。後者は有効性が確立された薬物療法もない。
強迫性障害に対するCBTはテレビでも繰り返し取り上げられるなど,よく知られるものになった。一方,実際に新患を受け入れ,治療している施設は患者のニードを満たせる程はない。そして治療者間で治療成績・期間のバラツキが大きい。CBTはどんな疾患や症状にも適応があるが,どの治療者でも同じようにCBTを適用できるわけではない。
パーソナリティーや発達の問題が合併している場合は?
パーソナリティー障害や発達障害についても適応がある。自閉性障害に対するコミュニケーショントレーニングは行動療法の一つである応用行動分析の最も良い適応である。性犯罪や反社会性パーソナリティーのように治療研究があるものがCBTしかなく,CBT以外には選択肢がないものもある。ただし,この場合,強迫性障害のような満足できる治療成績には到達していない。
なぜ有効か?
有効そうな理論や治療技法をいろいろ編み出しては,実験し,その中で良い結果が出たものを選んで行うようにしているからである。治療技法の中には,逆説志向のようにFrankl V.のロゴセラピーから借用されたもの,フラッディングのように精神分析から借用されたものもある。有効そうなら何でも試してみるのだから,有効になるのも当然である。
治療期間や回数は決まっているのか?
決まっていない。治療ガイドラインでは10~20回程度が目安になる。特定の恐怖の場合,1セッションだけで行えるとする報告もある。しかし,どの治療者でも同じように同じ回数と期間でCBTを適用できるわけではない。精神分析のようなほぼ一生というのはありえないが,学会などでのケース報告では毎週1セッションで1~2年というものも見かける。また,著者が行っている強迫性障害に対する3日間集団集中治療プログラム(3DI)を行う場合は,2ヶ月間で4~5回の個人セッションと,週末に行う3日間連続の集中プログラムでほぼ寛解に持ち込めるようにしている。一方,著者自身,過去に入院でCBTを同じ強迫性障害に行っていたころは,入院3~6ヶ月と数ヶ月の外来受診が普通であった。
他の治療と併用する場合の留意点は?
CBTそれ自体は併用を禁じているわけではない。厚生労働省のうつ病CBTマニュアルや他の治療ガイドラインもほとんどがさまざまな技法を一緒に使うようにしている。
併用が問題になるのは,CBTと他の治療法の目的が一致していない場合である。たとえば,不眠に対するCBTを行いながら,睡眠導入剤の頓服を増やすのは矛盾している。恐怖や回避行動を止めることが目的で,エクスポージャーを始めながら,抗不安薬を頓服させたり,気ぞらしやリラクセーションをさせることはエクスポージャーの効果を台無しにする。一般に,CBTは,今ここで患者が感じたり,考えたり,行動したりしていることを扱い,これからの行動を変化させることを目的にする。なぜ,こうなったか,誰のせいで,こうなったかのように原因を探求したり,加害者を捜したり,補償を求めたりすることがCBTの目的になることはまずない。従って,なぜ?誰のせいで?を解き明かすことが目的であるような治療法とは併用することはできない。
副作用や禁忌にはどんなものがあるか?
どんな疾患や症状にでも適応があるのだから,副作用や禁忌がそれ自体で問題になることはない。しかし,どの治療者でも同じようにCBTを適用できているわけではない。特にエクスポージャーや儀式妨害が不完全である場合や,CBTを行う理由や目的が患者自身にとって不明確な場合は,症状を悪化させる。たとえば,患者が治療を受ける目的が,原因探求や加害者捜し,補償要求であるならば,CBTを行うことで問題をかえって悪化させるだろう。
不安はどうして生じるのか
CBTは不安それ自体を病的なものとはみなさない。生きている限り,不安をゼロにすることはできず,変えられるのは,いつどこで不安が生じるか,不安になったときにどう行動するかだけである。不安がどうして,これこれこういう場合に生じるのか,については答えることができるが,そもそも不安がどうして生じるのか,については,生きているから,としか答えようがない。
CBTはマニュアル通り行うべきか?
違う。既存のCBT治療マニュアルは治療者をトレーニングし,効果を検証するために作られたものである。マニュアル通り行うことはCBTをやっていることの保証にはなっても,治療結果の保証にはならない。なぜなら,どの臨床試験でもマニュアル通りにやっている治療者個々人の間に大きな治療結果の違いが生じるからである。経験的には,マニュアルに従うよりも,患者の現在のニードや行動にそって治療を組み立てるほうが良い結果が得られる。マニュアルは治療がオートマチック(自動運転)になるためにあるのではない。実際の臨床では,マニュアル運転のためのマニュアルにならなければならない。
CBTの代表的な技法
セルフモニタリング
患者が自分自身で毎日の情動や思考,行動を日記形式で記録することである。不安発作や強迫行為のように回数や時間を特定できるものがあれば,回数や時間を記入する。全般的な気分や不安感の場合には,0(不快感・不安感なし)~100(最大の落ち込み・不安)のようなアナログスケールにして気分や不安を点数化してつけるようにする。セルフモニタリングは他の全ての技法の基礎になる。
セルフモニタリングは治療前に必要な標的行動の評価になる。またそれ自体も患者の行動を変える。セルフモニタリングを毎日行うことで,患者が自己観察行動をするようになり,客観的に自分を見るようになる。
治療者は患者に具体的な記入例を示し,回数や時間の計り方,点数の付け方を教えるようにする。セルフモニタリングの必要性やメリットも教えたほうが良い。最初のうちはとりあえず日記に記入したぐらいのレベルでも十分である。抜けている日があったり,標的行動を正確に記録しなかったりした場合は,指示通りにできていた日は何をしていたか,できない日はどうしていたかを話し合うようにする。その結果,セルフモニタリングの用紙や置いておく場所,記入する時間を変えたり,設定したりができる。
経験的に,最初の1,2ヶ月間はセルフモニタリングをするだけで,患者も治療者も増加させたいと願っている行動の頻度は増加し,減少させたい行動に減少することが分かっている。それ以降になると,これらの変化は落ち着き,プラトー状態になる。このときには行動が多い場合と少ない場合についての分析を行う材料が手元に残っていることになる。大人よりも学童が真面目に記入する。日記を書くことを学校から指示されて,慣れているからかもしれない。もし,本人がつけられない場合には同居する家族につけてもらうこともできる。
コラム法
認知再構成のためには必須の方法である。これも自己観察行動の一種である。とくに思考を観察することになる。セルフモニタリングがつけられるようになった後に行う。どのような思考も脈絡なく突然浮かんでくるわけではない。また思考が生じれば,その後の反応や行動がある。思考が生じる前の状況や刺激,思考の内容,その後の反応や行動を毎回記録するようにしたものがコラム法である。
思考の内容については,そのときに頭に浮かんだ考えやイメージをできるだけそのまま断定文・肯定文で書くようにする。たとえば,「どうして,私は何をやってもうまく行かないんだろう?」ならば,「何をやってみても私は失敗する」と書くようにする。「トイレで気になった汚れが自分の手についたのかもしれない」ならば,「便が自分の手についた」と書くようにする。最初は,とりあえず思いついたことを書かせ,それから修正していき,適切にかけるように指導する必要がある。
これを書くことが,エクスポージャーになることがある。患者の情動表現を見ながら,ある程度時間をかけて行う。
活動スケジュール法
不安障害が治るとは,不安に囚われている時間よりも,日常生活を本来の患者らしいあり方で生活している時間が多くなることである。本来,行いたいと患者が願っている健康行動をいくつか選んでおき,それを1,2週間分計画し,できたかどうかを記録するようにする。セルフモニタリングと組み合わせて行う。最初からから必ず計画し,記録することは次回の受診予定である。
モデリング
患者にある行動を学習させるとき,その行動を実際に行っている他の患者や人を見せることである。患者が他者の行動をよく観察すること,行動を模倣することが含まれる。また,他者がエクスポージャーしている場面を観察することで,不安が起こったり(代理エクスポージャー),脱感作されたりする。モデルがいるような社会的場面にさらすこと自体が,患者が自分自身の内部の不安に向けていた注意を,周囲に向かわせるきっかけにもなる。ビデオなどで代用することもできるが,実際の患者や治療者がモデルになる方が強力であり,患者がモデルに年齢・性別,症状重症度などの共通点が多いと,模倣が起きやすくなる。
エクスポージャー
恐怖や不安が生じたとき,それらを打ち消したり,逃避したりするとその場は楽になる。一方,これを繰り返すことが,恐怖や不安反応がさまざまな事物に広く条件づけられることを助けることになる。何も考えないよう,何も浮かばないよう,何もしないよう避けたり,寝逃げしたりしていれば恐怖や不安は起こらず,楽だが,長く続けると抑うつ状態になる。何もしないでいることはやる気や楽しみを奪うからである。しかし,なんとか行動しようとするときには,以前よりも大きな恐怖や不安が襲ってくることになる。エクスポージャーとはこの悪循環から逃れる手段である。一般的には不安を惹起する刺激にさらすことだが,アルコール依存症や買い物依存症のように酒や商品など衝動を惹起する刺激にさらすこともエクスポージャーである。
恐怖や不安を乗り越えるために,その場で感じられる最高の不安を経験する必要がある。エクスポージャーは将来の不安を下げるために今の不安を上げるという逆説的なやり方である。強迫性障害の場合は,エクスポージャーの後にも手洗いや確認の妨害を2,3日間続ける必要があり,これをエクスポージャーと儀式妨害(ERP)と呼ぶ。エクスポージャーも学習の機会の1つだから,1回だけでなく繰り返して行い,身につける必要がある。
治療者の補助付きエクスポージャー
エクスポージャーの1回目は患者一人では難しい。治療者が実際にエクスポージャーを自分でやってみせて,次は患者が自分でするように促し,させてみて,少しでもできたら誉める,ということを行う。次第に難しい課題に向かっていくようにする。
セルフエクスポージャー
治療者の補助付きでできるようになっても,患者一人でできなければ,いつまでも路上試験に合格しない,仮免中のドライバーのようなものである。患者が自分一人で課題をこなすことを毎週1回は行うようにする。
治療効果維持のためのエクスポージャー
いったんできるようになったことも,1,2ヶ月怠るとまたできなくなる。数ヶ月に1回程度のカウンセリングを行い,治療の効果を保つようにする。
イメージ(言語,認知)エクスポージャー
エクスポージャーの対象となるものは外部の事物だけではない。臓器の内部感覚と腸管運動が条件づけられるように,心の中で思い浮かぶこともエクスポージャーの対象になる。認知エクスポージャーと呼ばれることもある。全般性不安障害の患者に対しては朝の決まった時間に集中的に心配事を考えるようにさせる。“心配エクスポージャー”と呼ばれる。
課題分析
最初は不可能に見えるような大変な行動課題であっても,細かく細分化していけば,こなせるような課題になる。不安刺激に対するエクスポージャーも細かな段階に分ければ,ステップバイステップでこなしていけるようになる。エクスポージャーを始める前に,不安刺激を弱いものから強いものへ段階をわけてリストアップすることを,不安階層表(ハエラキー)を作るという。この過程自体が,患者の症状を行動分析していることになる。
スキルトレーニング
病歴の長い患者の場合,エクスポージャーなどによって不安が減弱しても,その代わりに行うべき行動レパートリーが不足している場合がある。特に全般性社交不安障害の患者の場合は,対人スキルが不足している。こうした患者の場合には,不安症状の治療だけではなく,主張性訓練や生活技能訓練などが必要になる。こうした患者が身につけたことがない新しいスキルをトレーニングで身につけるようにすることをスキルトレーニングという。行動分析学でいうシェイピングやモールディング,モデリング,行動リハーサルなどが使われる。シェイピングのためには患者の行動の変化を微細に観察し,望ましい行動が生じたときにすかさず小さな強化子を繰り返し提示できるような,細やかなセンスが治療者に必要である。
終わりに
精神分析と違い,CBTは学派や流派を作らない。師弟関係はあったとしても曖昧であり,そもそも必須ではない。師匠を持たず,本だけで自学自習しただけの者がCBTをマスターしたことになることも不自然なことではない。少なくともCBTの創始者は,実験心理学の経験だけを頼りに,誰からも学ばずに臨床に打って出たのである。しかし,現代におけるCBTが置かれた状況を考え,そして他の同様な技術が持っている習得システムと比較したとき,CBTを習得する方法が書籍やワークショップに限られているのは望ましいことではない。精神分析が持っているような師弟関係に基づく習得システムもこれから必要になるだろう。不安障害に対するCBTの臨床からそのようなモデルが始まることを望んでいる。
文献
- Bykov, K., Pavlovian contemporary psychiatry in the USSR. Am J Psychiatry, 1959. 116.
- Garcia, J., D.J. Kimeldorf, and R.A. Koelling, Conditioned aversion to saccharin resulting from exposure to gamma radiation. Science, 1955.
- Bovbjerg, D.H., et al., An experimental analysis of classically conditioned nausea during cancer chemotherapy. Psychosomatic medicine, 1992. 54(6): p. 623.
- Association, A.P., Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III). 3rd ed. 1980, Washington DC, USA: American Psychiatric Press.
- Andreasen, N.C., DSM and the death of phenomenology in America: an example of unintended consequences. Schizophrenia Bulletin, 2007. 33(1): p. 108.
- 原井宏明, 岡嶋美代, and 中島俊, 社会不安障害の薬物療法 ―臨床試験と一般臨床の違い・認知行動療法との併用―. 臨床精神医学, 2007. 36(12): p. 124-138.