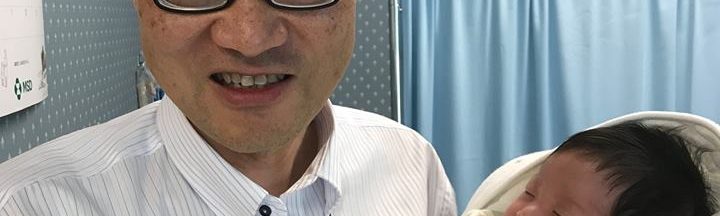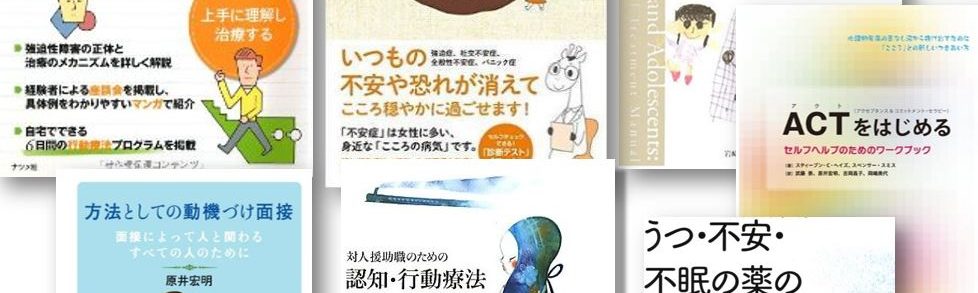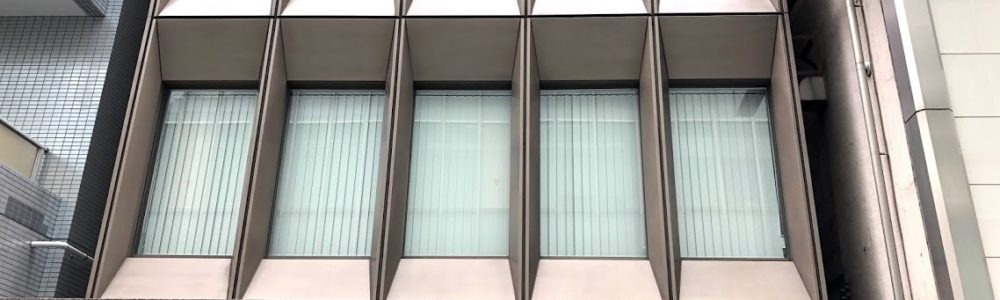和文・英文要約
未来予測には過去の振り返りが必要である。過去の資料を調べ、過去に未来をどのように見ていたかを調べた。その結果、第6回大会の時点ですでに行動療法の未来について議論していたことがわかった。一般にまだ知られていない段階で、行動療法の停滞を心配していた。認知行動療法に名を変え、普及に力点を置くことで危惧されていた停滞を乗り越えたようにみえるが、実際の治療成績・理論的発展という点では、1980年代に危惧されていた停滞が現実になっている。筆者自身が「行動療法」を知ってから40年になる。認知行動療法の50年は筆者のキャリアともほぼ重なっている。筆者の個人史と過去の資料、そしてRogersのイノベーションの普及理論を折り重ねながら、現在、何が起きているのか、自分自身が何をすべきかを考えた。
Predicting the future requires looking back. This paper examined past materials to see how the future was viewed in the past. It was found that the future of behavior therapy was already being discussed as early as the 6th annual meeting. They were concerned about the stagnation of behavior therapy even when it was unknown to the general public. Although it seems to have overcome the feared stagnation by changing its name to cognitive-behavior therapy and focusing on dissemination regarding treatment outcomes and theoretical development, the stagnation feared in the 1980s became a reality. It has been 40 years since the author was introduced to the concept of “behavior therapy. The 50 years of its history overlap with the author’s career. By juxtaposing the author’s personal history, past materials, and Rogers’ diffusion theory of innovation, I have considered what is happening today and what I should do.
はじめに
未来について論じることをどう考えたらよいのだろうか?人類が言語を獲得したときと同時に未来を予測する能力も得たと考えられている。最古の未来予測の実例として、紀元前3000年頃にメソポタミア文明が月と太陽の運行をもとにした暦を作った事実がある。これによって人は季節の変化や洪水の時期を正しく予測できるようになった。紀元前1300年、中国文明は甲骨文字を使用して未来を占っていた。占いの結果が正しかったかどうかはさておいて―現代でも占いは広く行われているが、甲骨文字占いを信じる人はいない―、人は未来がどうなるかを知りたがり、語りたがる。未来を知ったとすれば、可能な限りその未来を変えたいと願う。
私は精神科開業医であり、毎日2、30人の患者さんを診療している。受診する患者の場合の願いも同じである。患者が治療者に願うものは二つある。一つは自身の未来予測と、もう一つは、もし治療によって変えられるなら、望む方向に未来を変えてもらうことである。この二つの願いは2019年に「エクスポージャー療法センター」として行動療法を中心に行うメンタルクリニックを開業した私にとっても気になることかもしれない。まず、私自身と「行動療法」の関わりを振り返ってみよう。
私と行動療法
私が日本認知行動療法学会に初めて参加したのは39年前、第12回大会のときである。山上敏子先生の勧めだった。この学会の未来あるいは予後がどうなるかは、私にとっても気になる。行動療法(Behavior Therapy)という名前が初めて文献に登場するようになったのは1950年代末であり、これは私が生まれた年代と重なる。私は自分の年齢と行動療法のそれを重ね合わせて考えてしまう。生まれたときの私は行動療法など知らず、医学部でも聞くことはなかった。初めて名前を耳にしたのは医学部卒業後、ミシガン大学に留学したときである。デトロイトのランドマークである73階建てのルネサンス・センターを見に行ったとき、数人のアメリカ人が集まっており、彼らはこれから広場恐怖を克服するためにグループでエレベーターに乗るという。このとき彼らが使った言葉がBehavior Therapy(行動療法)、Exposure(曝露療法)だった。
この後、中井久夫教授がいた神戸大学で研修したときも、行動療法を知る人は誰もいなかった。中井久夫先生は強迫症についてもかなり書き残していて、その中には強迫症を専門にしている私も驚くような的確な記述がある。しかし、治療としてはブロマゼパム(レキソタン®)を処方するぐらいしかできず、神戸大学精神科において治療によって強迫症が治った患者はいなかった。
近くの兵庫医科大学に久野能弘先生がいたことを知るのは私が肥前療養所に就職した後である。精神科医になってからも精神医療の領域で精神療法・心理療法といえば精神分析であり、行動療法・CBTは少数派である。1999年に内山喜久雄先生は「日本の行動療法の四半世紀一学会創立25周年にあたって一20年前を振り返る」(内山, 1999)において、このように書いている。
圏内の年次大会開催地にしても、過去25回中、関東12回、九州6園、関西3回、北海道、東北、中部、中国各I回となっており、地域的に偏りがうかがわれ、会員数もまた同様の傾向にあることもその一因であろう。首都圏、九州、関西はともかくとして、その他の地域でもさらに会員数が増し、活動が活発化することが望まれる。本学会の創立以後の展開は、発足時の200余名から25年経過した現在、研究内容や研究水準は別として、会員数という点ではかならずしも当初予想した程の伸び数に達していない。
行動療法学会の会員数が1000名の大台を超えたのは2004年である。6月11日の時点で1024名になった(行動療法学会, 2004)。その約十年後2015年9月には2053名になった(認知・行動療法学会, 2016)。学会誌の会務報告に基づく会員数のグラフをFig.1に示す。
Fig. 1 認知行動・療法学会(旧行動療法学会を含む)の会員数
技術の普及に関する社会学的研究としてはEverett M. Rogersによる「イノベーションの普及」(Rogers, 2007)がよく知られている。Fig.2に彼による普及過程を示す。普及におけるSカーブは学会会員数のグラフの形に似ている。学会の会員数は最初の25年間の停滞期を脱して、彼の言う「離陸」をしたと言えるだろう。
Fig. 2 普及過程(Rogers 2016 イノベーションの普及 図1-2)
さらに彼による5つの採用者カテゴリー;イノベータ、初期採用者、初期多数派、後期多数派、ラガードをFig.3に示す。
Fig. 3 革新性に基づいた採用者カテゴリー(Rogers 2016 イノベーシのョンの普及 図5-3)
彼の分類に従えば、今は後期多数派がCBTを採用する時期になったと言える。39年前、行動療法は少数派の中の少数派だった。今は、会員数の点で日本精神分析学会の会員数(2024年1月で2488名)と肩を並べるようになった。約40年前、中井久夫や神田橋條治を信奉していた他の研修医仲間に背を向けて、山上敏子を選んだ私を褒めてやりたい。一方、これは、これからCBTを選ぶ人たちと40年前に選んだ私との違いも意味している。初期採用者であった私は後期多数派に対して何を伝えれば良いのだろうか?この疑問に答えるために、これからは学会誌に掲載された未来予測を参考にしながら、CBTの未来を考えてみよう。
学会誌から未来を予測する
未来予測についてはよく知られているものの一つがデルファイ法である。専門家の集団に対して同一の問いかけを繰り返し行い、意見をまとめるものである。認知行動療法学会は今までに数回にわたって未来予測をテーマにしたシンポジウムを行っている。これらの意見をまとめればデルファイ法のようになる。彼らの意見を検索してまとめることにする。
検索結果とまとめ
学会誌から未来に関するものを検索すると次のものが見つかった。
1981年 内山「行動療法の沿革と展望」(内山, 1981)、木村、茨木、高石、藤田、滝沢「行動療法の未来」
1997年 園田「私の行動療法 過去・現在・未来」(園田, 1997)
2001年 内山、上里、高山によるシンポジウム「わが国の行動療法」
2015年 神村、五十嵐、若島、鶴、熊野、井上によるシンポジウム「行動療法・認知行動療法の現在と未来」坂野による教育講演「認知行動療法From where to where?」
2020年 岡本「脳からみた認知行動療法とその近未来的展開」(岡本, 2020)
それぞれを見直すと興味深い。1981年に高石は次のように述べる(高石, 1981)。
わが国の精神医学での未来について附言するならば,残念ながら行動療法の利用は当分停滞がつづくと思われる。その第一の理由は,わが国は経済先進国のうちでは名だたる心理療法の不毛地帯であり,行動療法だけがその例外とは思えないからである。不毛の原因は,心理的な治療に対しての報酬を考慮しようとしない支払い制度にあり,その結果,心理療法にうちこもうとする精神科医が育ちにくいことは,オペラントの原則からも頷けるところである。
行動療法不振を予測するもう一つの理由は現在のわが国の精神医学界には行動療法のある特徴になじみにくい風潮があるように思えることである。
たとえば,治療の場における統制研究や,治療的指示による患者の操作性,といった側面である。これらの批判に対する討論は他の機会にゆずるとして,かくして,わが国の行動療法は,当分の間,大学病院や研究所で細々と続けられるであろう。
それから20年がたった2001年に上里は行動療法が混迷しているとする(上里, 2001)。
1.行動理論の停滞:行動療法の基礎理論としての行動理論に斬新な提案がなく,技法と理論との解離が目立つようになった。
2.行動療法の定義や概念の不鮮明化:認知行動療法などのいわばソフトなアブローチが台頭するとともに,行動療法の定義や概念が曖昧になったことは否めない。ここらで,行動療法とは何かをあらためて検討する必要があるのではないか。
3.治療体系や治療理論なのか単なる技法なのか:他の心理療法のように,独自の人間観を持つ治療理論なのか,それとも,技法の集積なのかが問われる事態になっているようである。単なる技法とすれば,学会の存在の意味が問われるのではないか。また,臨床で用いられている技法が判りにくく行動療法の特徴とされる明確性を欠くものも少なくない。
4.会員の拡がりと多様化:学会も30年に近い歴史を重ね,会員の層が3世代にわたる状態となり多様化している。学会は研究発表の場というよりは,学習の場として機能することが多くなっているかのようである。とすれば,学会の大会の持ち方を考える必要がある。これから刊行される予定の標準的なガイドブックがそれに応えることが期待される。機関誌の発行の遅延もこのことと無関係ではない。
5.研究発表や論文の低迷:うえに挙げたことを反映して,大会や機関誌の論文が低迷していると思えてならない。それは,行動療法が成熟の域に達したから起こる現象とも思えないのである。とりわけ,臨床を大切にしなければならない学会なのに,症例報告が他の学会と比較しても,遥かに劣るのではないかと危惧される。ケーススタディやスーパービジョンなどについても大会で議論したいものである。
このように,わが国の行動療法は飛躍的に発展したが,これからの一段の成長をはかるためには,険しい関所に差し掛っているといえるのではないか。
2015年に「行動療法・認知行動療法の現在と未来」と題したシンポジウムで、神村栄一と五十嵐透子が司会になり、学会側を代表して熊野宏昭と井上雅彦が、他の心理療法を代表して若島孔文と鶴光代が話題提供した。どの演者も行動療法・CBTにエビデンスがあること、さまざまな領域に普及していく過程にあることについて意見が共通している。違いは現在のあり方に対する批判である。
若島は次のように言う(若島, 2015)。
二つの視点から認知・行動療法を眺めている。一つは行動理論、エリス、ベックらの認知理論に基づく心理療法であるということ。もう一つはあらゆるものの寄せ集めと病気や障害ごとに作成された方法。前者はブリーフセラピーと親和性を持つが、後者はなんだか右から左までならべたM主党のようである。
M主党とは当時存在した民主党のことである。政権交代を目指して、ラディカルな社会主義者から保守派まで集まった党だった。保守派は反共色が強く、社会主義者を排除しようとした。野党転落後、この党はばらばらになることになる。認知行動療法学会も徹底的行動主義者―英語ではラディカルである―から、認知療法派まで集まっている。徹底的行動主義者から見れば、認知療法派は排除の対象だろう。日本にはもう一つ、日本認知療法・認知行動療法学会があるが、彼らは基本的にベッキアン(A. T. Beckの信奉者)である。彼らは方法論的行動主義者とも混ざらないはずだ。若島は「エリス、ベックらの認知理論に基づく心理療法である」に批判的である。一方で、井上雅彦は次のように論じる(井上, 2015)。
臨床研究のアウトカムが尺度データの群間比較データに基づくRCT に偏重している点、またその臨床も診断名や尺度得点からターゲットや技法が安易に選択され、パッケージ化された治療計画を安易に進めてしまう危険性を危惧する。行動論に基づくアプローチの特徴は、心理諸活動を含む行動と環境要因との因果関係をクライアントひとり一人と共有しながら進めていくことにある。ターゲット行動選択に関するケース・フォーミュレーションとシングルケース研究デザインの重要性について論じたい。
井上は2024年でもシングルケース研究デザインを単一事例研究法と言い換えて、同じ主張をしている(井上, 2024)。
単一事例研究法は、環境(治療的介入)との関数関係によって変化する従属変数としての行動変化にしたがって仮説を修正し、柔軟な介入を可能にする。行動を科学的に観察し、測定していくためには、できるだけ自動的に、機器によって、観察時間全体にわたって、連続的に測定することが望ましい(中略)単一事例研究法は、その対象が認知であっても活用可能でありCBT においても、理論的な違いを超えて採用されるメリットは大きいと考える。様々なテクノロジーの進歩によって単一事例研究法が高次に発展していくことで理論的対立を超える未来を期待したい。
井上にとっては単一事例研究法の発展によって若島のいうM主党内部の対立が解消すると期待しているかのようである。
坂野による教育講演「認知行動療法From where to where?」はCBTについて、普及の結果として誤解が広まっているとする(坂野, 2015)。
CBTは単なる治療法というよりもむしろ、「問題」と呼ばれる状態をどのように理解し、その修正・変容が必要な時にはどのように働きかけるか、そして、働きかけのプロセスをどのように評価し、再現可能なものとしていくかを理解するための理論的・実践的・哲学的枠組みでもある。
この坂野の主張は井上が繰り返し主張していることと重なる。ケース・フォーミュレーションと単一事例研究法は同じことを言っている。しかし、上里や坂野、井上の繰り返しの訴えにも関わらず、実際には一般にはCBTに対する誤解が広まっている。坂野が指摘する誤解は4つある。
- CBTは知的側面を扱うという誤解
- 問題解決に向けて「ポジティブ思考」を身につけることが大切だといった誤解
- CBTは単なる技法の集合体であり、技法をマスターすることがCBTの習得であるという誤解
- CBTのマニュアルを熟知し、使いこなすことが大切であるという誤解
もし、2001年の上里が坂野の論文を読んだとしたら「私の言ったとおりになった」と言うかもしれない。
坂野は2015年ごろにはあちこちで広まり始めた「第三世代の認知行動療法」と「動機づけ面接」にも批判の目を向けている。動機づけ面接(Motivational Interviewing, 以下MI)については、私は日本動機づけ面接学会の創設者であり、現在は名誉理事である。私はこの20年間、MIの普及の最前線に立ち、主要な教科書は私が翻訳した。坂野の批判は私に向けられている。私は何を間違ったのだろうか?こうした間違いは他の領域でも起こりえるのだろうか?イノベーションの普及について考えてみよう。
イノベーションの普及
イノベーションの属性
Rogersはイノベーションの普及に関して、5つの属性があるとする。1)相対的優位性、2)両立可能性、3)複雑性、4)試行可能性、5)観察可能性である。
相対的優位性は既存のものよりも良いと知覚される程度である。エビデンスの強さはもちろんだが、加えて採用することによる採用者が得る社会的な威信や便利さ、満足感も重要な要素である。Rogersは、客観的なエビデンスの強さよりも、採用者個人がどう知覚するかが普及速度に大きく影響するという。両立可能性とはイノベーションが既存の価値観、過去の体験、採用者のニーズと相反しないと知覚される程度である。既存の方法と両立しやすいアイデアは採用しやすくなる。CBTの技法の中で、認知療法と応用行動分析を比較すれば、前者の方が両立可能性が高い。複雑性はイノベーションを理解したり、使用したりするのが相対的に困難であると知覚される程度である。低い方が普及が早い。認知療法と応用行動分析では後者の方が複雑性が高い。試行可能性は初心者の段階でイノベーションを体験しうる程度である。全くの初心者が、研修会に参加したその日からそのアイデアを試みることができる場合、そのイノベーションは早く採用される。CBTの技法の中で、曝露反応妨害法と動機づけ面接を比較すれば、ワークショップを受講した初心者がその日から使ってみて、効果を感じることができるのは後者である。前者は参加当日から実際に使えるチャンスはまずないし、患者に対してすぐ使おうとしても失敗し、二度と使わなくなる可能性の方が高い。観察可能性とは、イノベーションの結果が他の人たちの目に触れる程度である。採用者の友人が目の前でやっているところを見せ、周りが簡単に模倣できるものは普及しやすい。
たとえば、応用行動分析に基づく単一事例研究法は優位性・両立可能性は高い。歴史も長い。1975年にすでに山上が反応妨害法について、手続きを9回反復するという徹底的な単一事例研究法を用いて、反応妨害法の優位性を証明している(山上, 1975)。これだけ歴史があり、優位性もある技法が普及しないとしたら、要因がある。複雑性の高さ、試行可能性・観察可能性の低さを考えることができる。単一事例研究法はその場で見せて周りがすぐ模倣して広まるようなものではない。
概念的なものであるが、CBTの諸技法についてこれらの属性を比較したものをTable1に示す。
| CBTの諸技法
治療パッケージ |
応用行動分析 | 曝露療法 | 動機づけ面接 | |
| 相対的優位性 | さまざま | 高い | 高い | 高い |
| 両立可能性 | 高い | 低い | 低い | 高い |
| 複雑性 | さまざまだが、簡単なものも多い | 高い | 簡単だが、成功させるのは困難 | 低い |
| 試行可能性 | 高い | 低い | 低い | 高い |
| 観察可能性 | 高い | 低い | 高い | 高い |
Table 1 CBTの技法の属性の概念的な比較
消えた技法と生まれる技法
普及は消えるものもあることを意味している。CBTの中には忘却されてしまった技法もたくさんある。私が最初に参加した第12大会の発表論文集に取り上げられている主だった技法や概念を列挙してみる。
- 対人スキル訓練(SST)
- モデリング、トークン・エコノミ一法
- フリーオペラント法(HIROCo)
- Activity Scheduling
- バイオフィードパック
- セルフモニタリング
- セルフエフィカシー
- 半睡暗示法による括抗制止
- 自律訓練法
発表や研修会で表立って取り上げられることは少ないが、SSTとモデリング、トークン・エコノミ一法、セルフモニタリングは現在も活用されている。以前は頻繁に取り上げられたセルフエフィカシーも今はほとんど聞かれなくなった。
次に、この2,3年の学会発表から、目新しいと思われる技法を列挙する。
- ポリヴェーガル
- MBCT(Mindfulness-Based Cognitive Therapy マインドフルネス認知療法)
- CT-R(Recovery-oriented Cognitive Therapy リカバリーを目指す認知療法)
- CBT-I(不眠のCBT)
- TSプロトコール(杉山登志郎が発案したトラウマ治療法)
- 条件反射制御法(平井愼二が発案した治療法)
- 言語的価値低減法(岡嶋美代が発案した治療法)
38年前と大きく違うのは具体的な技法や概念ではなく、さまざまな技法を組み合わせた治療パッケージが取り上げられるようになったことである。たいていの場合、創始者がおり、その創始者がマニュアルを準備し、研修会を行い、普及活動を行っている。こうした治療パッケージの流行についてRogersの考えに応用しながら考えてみよう。
再発明とチェンジエージェント
Rogersによれば、イノベーションの普及において元の通りで普及することは少なく、少なからず採用者によって変更や修正が加えられ、再発明が生じる。融通が利くイノベーションであればあるほど、採用者による再発明が増え、さまざまな方法でさまざまな用途に普及することになる。採用者の一部は自身の置かれた状況に合わせて他の人のイノベーションを換骨奪胎したものを発案し、できれば自分の名前も付けて、自分の地位を向上させたいと願う。あるイノベーションの再発明が簡単な場合は、普及がより速やかになり、その採用がなお一層持続されることになる。再発明をする人は、それを普及させる人、チェンジエージェントになる。彼らには他より優位に立てるというメリットがある。
今も新しい技法、治療パッケージが生まれてくるCBTは再発明の宝庫であり、それが今のCBTの普及につながっている。一方、再発明を拒む日本行動分析学会のような学会もある。「臨床行動分析」という言葉を最近はよく聞くようになったのは、CBTの再発明では望ましい結果につながらないことに気付く人が増えたからだと思いたい。
学会の外でひろがる再発明とチェンジエージェント
CBTを再発明し、普及しているチェンジエージェントは学会外にもある。たとえばチックに対する治療としてエビデンスがあるHabit Reversal Training(習慣逆転法、以下HRT)を日本CBIT(シービット)療法協会という団体が普及させている。協会のHPに代表の木田哲郎のプロフィールがある。もともと本人がチック症で悩んでいた。HRTによって改善し、それを日本で広めるためにキダメソッドと名付けて、普及活動を行っている。第65回日本小児神経学会にて発表もしている (木田, 2023)。HRTはB.F. Skinnerの弟子であるN.Azrinが開発した行動療法であるが、単一事例研究法や基礎的な学習理論を知らなくても、再発明は可能であり、その方法に自身の名前を付けて、チェンジエージェントになることも可能である。
今後、認知・行動療法学会とは関係ないところで、CBTは新しい再発明と再発明者の名前を付けた治療パッケージを次々生み出し、何がCBTなのか?について患者や医療関係者が頭を悩ますようになるだろう。行動分析学会と違い、認知・行動療法学会は再発明に対しておおらかである。それが学会会員数を増やすことにつながっているが、同時にこれは上里や坂野が示した懸念を大きくすることにもなっている。
おわりに
私もチェンジエージェントの一人である。CBTについては他にも大勢いるが、MIに関しては日本におけるチェンジエージェントの第一人者だった。MIはCBTよりもさらに幅広く、臨床を全く持たない人の間にも普及してきた。世界規模でのチェンジエージェントの育成を30年以上続けてきたこともそうなった理由である。MIではこのチェンジエージェントのことをMINTメンバーやMIトレーナーと呼ぶ。2003年は1人だけだった日本人MINTメンバーが、2024年には100人を優に越え、私にも誰がMINTメンバーなのか分からなくなった。広げた結果がどうなったかについて私にも分からないし、一人ひとりの実践の品質は当然、違うはずだが、誰がそうなのかは私には答えられない。坂野はそれを無責任と呼ぶだろう。
27歳の私にとって行動療法はイノベーションだった。内省心理学中心だった精神医学・臨床心理学の世界に心を持たないとされた動物を扱う実験心理学を持ち込み、心とされていたものを変えることができることを実証していた。12回大会の抄録を見直すと、インポテンツに対する行動療法(阿部, 1986)など、多領域からの驚きのトピックばかりである。今の学会は再発明とチェンジエージェントの普及自慢ばかりになり、驚きを生まなくなっている。学会の役割は、もともとは他領域の人と出会い、既存の思考にとらわれない新しい発想ができる場所を提供することだったはずだ。
今の私には残された時間が少ない。与えられたものを丸のみする人、改変して再発明する人に対して私にできることは少ないが、38歳の山上敏子(山上, 1975)のように強迫症に対する曝露反応妨害法の優位性を疑い、ABCデザインによる反復測定を9回も繰り返すような疑り深い人には私ができることがあるだろう。行動療法の創始者たちには懐疑主義があり、周りが当然と思うものをそのまま受け取ることをしなかった。自分の目で事実と確かめるまでは普及させることもしなかった。同時に新しいものに触れることにも貪欲だった。そのような懐疑心と好奇心を持つ人に応えられるような仕事を残りの人生の間にしていこうと思う。
引用文献
Rogers, E. M. (2007年). イノベーションの普及 (三藤利雄, 翻訳者). 翔泳社.
阿部輝夫. (1986年). 未完成婚とセックス・セラピー. 日本行動療法学会大会発表論文集12巻, 21.
井上雅彦. (2015年). 行動療法・認知行動療法の現在と未来. 日本認知・行動療法学会大会発表論文集41巻, 25.
井上雅彦. (2024年). 認知行動療法の近未来. 日本認知・行動療法学会大会発表論文集50巻, 86–87.
園田順一. (1997年). 私の行動療法-過去 現在 未来. 日本行動療法学会大会発表論文集23巻, 27.
岡本泰昌. (2020年). 脳からみた認知行動療法とその近未来的展開. 日本認知・行動療法学会大会発表論文集46巻, 43–44.
原井宏明. (2024年). 書評 新装版ことばと行動. 精神療法, 50(2), 139–140.
行動療法学会. (2004年). 2004年度第2回常任理事会議事録. 行動療法研究, 30(2), 138.
高石昇. (1981年). 行動療法の未来-精神医学の立場から. 行動療法研究, 6(2), 12–17.
坂野雄二. (2015年). 認知行動療法:From where to where? 日本認知・行動療法学会大会発表論文集41巻, 2.
山上敏子. (1975年). 反応妨害法について. 日本行動療法学会大会発表論文集1巻, 60–61.
若島孔文. (2015年). 行動療法・認知行動療法の現在と未来. 日本認知・行動療法学会大会発表論文集41巻, 25.
上里一郎. (2001年). わが国の行動療法―発展と混迷. 日本行動療法学会大会発表論文集27巻, 43–44.
内山喜久雄. (1981年). 行動療法の沿革と展望. 行動療法研究, 6(2), 3–10.
内山喜久雄. (1999年). 日本の行動療法の四半世紀 学会創立25周年にあたって. 行動療法研究, 25(2), 1–9.
認知・行動療法学会. (2016年). 一般社団法人日本認知・行動療法学会 2015年度第3回理事会議事録. 認知行動療法研究, 42(2), 279.
木田哲郎. (2023年). 明日から実践チック・トゥレット症の新しい治療 チックのためのCBITキダメソッドの実際とその効果について. 脳と発達55巻, S154.