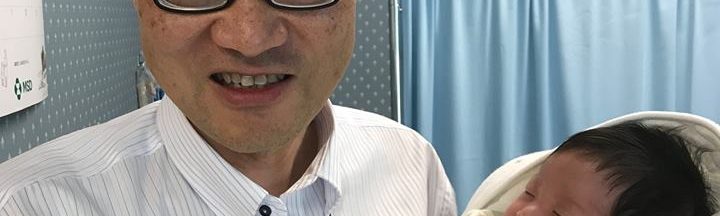軽症例に対する精神科薬物療法のあり方 -軽症うつ病に対する精神科薬物療法
筆頭著者名(和文): 原井 宏明
所属1(和文):医療法人和楽会なごやメンタルクリニック
所属2 (和文):国立病院機構菊池病院臨床研究部院外共同研究員
共著者名(和文):橋本 加代
所属 長嶺南クリニック
I. 「軽症うつ病に対する精神科薬物療法はどうしたら良いのか」
1. 30年前を振り返る
うつ病に薬物療法を行うべきかどうかは古い話題である。筆頭著者の原井が中井久夫教授が率いる神戸大学清明寮で研修医を始めたときから議論されている。DSM-III(1)が生まれた頃,約30年前のことだから,今と背景は違う。当時のメインの抗うつ薬は三環系だった。新規抗うつ薬は当時もあったがそれはマプロチリンなどの四環系だった。今の新規抗うつ薬は選択的セロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors,以下SSRI),セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(Serotonin & Norepinephrine Reuptake Inhibitors,以下SNRI),ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬 (:Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant,以下NaSSA)である。当時の新型うつ病は仮面うつ病だった。Smiling Depressionとも呼ばれ,笑っている人でもうつ病を疑えというものだった(1)。非定型もあったがうつ病ではなく,非定型精神病だった。
診断方法も違う。神戸大学での研修医時代,DSMならぬDSEが診断であった(D=うつ,S=統合失調症,E=てんかん)。カルテの病名もこの三つのどれかだった。この三つは三大精神病であり,精神病こそが大学病院精神科が扱うべき疾患だった。精神病そのものは治せないかもしれないが,入院や鎮静,デイケアなどによって保護やリハビリをする必要があった。まれにn=神経症とつけることもあったが,nの患者は本来は来るべきではない患者だった。まとめればDSEn(ディー・エス・エヌ)診断と呼べるだろう。軽症うつ病はnになる。不安障害という概念はなく,軽症はまとめてnだった。そしてnを特異的かつ確実に治すような治療法は当時はなかった。治せない上に入院や保護,リハビリが不要な患者を大学病院で診続ける意義はない。「病気ではないから気にするな」と伝えることが精神療法だった。
精神療法と比べると抗精神病薬の効果ははっきりしている。問題を起こす患者がいれば看護師長が注射しろと研修医の私に命じていた。診断がSではないからと私は抗議したが,抗精神病薬の注射の効果は幻覚や妄想だけではなく,病棟内での人間関係のトラブルや強迫行為,嗜癖にも及ぶと思われているようだった。オーベンからは脳波だけはきちんと評価できるようになれと指導された。脳波以外は診断も含めて精神科医の仕事のほとんどは曖昧で医学と呼ぶに値しないというのが理由だった。精神医学は独自の哲学に基づく実用性無視の学問,「医学」と呼べないマイナー科という位置づけの方が主流だった。当時は,エビデンスに基づく医療(Evidence Based Medicine, 以下EBM)(2)という概念はなかった。
「認知行動療法」もなかった。精神療法イコール精神分析だった。笠原嘉の小精神療法はあった。その原則は病人全体に通じるような,1)休息させる,2)病気の間は非難しない・励まさない・決めさせない,3)希望的観測を伝える,だった。これだけなら精神科で精神療法を研修する必要はない。風邪を引いて寝ている患者を診る内科医も同じことをするだろう。行動療法がなかったわけではない。しかし,九州などごく一部で行われているだけで,普通の精神療法家から見れば行動療法とは人を動物扱いし,飴と鞭で支配する下品な代物だった。1980年代は認知行動療法という言葉が生まれた時期である。頭に”認知”をつけることで行動療法をより人間的なものとして受け入れてもらいやすくする狙いがあるようだった。
今は,どれだけ30年前から変わったのだろうか?
2. 今
はっきりと変わったものは数である。うつ病患者の数は,1984年,入院・外来合わせて11万人だった(3),今は100万人を超えている。精神科・心療内科の外来クリニックの数が増えた。日本精神神経学会も大きくなった。現在の会員数15,155人,2013年5月の第109回学術総会の参加者は6,400人を超えた。1980年代は会員数5,000人台,学術総会参加者は1,000人あれば多い方だった。1997年,93回大会のときでも1,700名である。
治療法も増えた。薬だけではない。認知行動療法が加わった。精神分析と違い,抗うつ薬とプラセボと比較したランダム化比較試験(4)の結果と一緒に紹介され,”抗うつ薬と同等のエビデンス”という肩書きもある。エビデンスのためにDSMがいる。エビデンスのほとんどが欧米からの輸入品であり,輸入品を日本で使うためにはDSEnでは都合が悪い。
数の増加と,選択的セロトニン再取り込み阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI)とDSM,EBM,認知行動療法の普及はほぼ同時に起こっており,それぞれが関連していると考えるのが自然である。新規抗うつ薬の増加と,診断基準とエビデンス,認知行動療法の普及によって,うつ病の患者は1980年代よりも治るようになったのだろうか?あるいは治療のメニューの増加に合わせて,どの患者はどの治療がマッチしているとわかるようになったのだろうか?もし,そうならばうつ病の患者はここまで増えないはずである。新型うつ病や難治性うつ病という概念がでてくる必要もない。学会が大規模化し,治療メニューが増え,診断がより正確になり,判断に役立つエビデンスが増える,このような良い進歩が起これば起こるほど,かえって新型や難治性の敵が増えているように見える。まるでベトナムやアフガニスタンで泥沼の戦争に追い込まれた二大超大国のようだ。泥沼から抜け出す努力はもちろんある。日本うつ病学会が出した治療ガイドラインはその1例だろう(5)。それで上手く行っているのだろうか?
精神神経学会の学術総会に参加する人が増えた,しかも真面目に勉強する人が増えた。知識に対する欲求が増え,知識総体も増えた,なのにうつ病治療のアウトカムの改善はない,むしろ知識に振り回され,混乱が増しているように見える,それでも原井が参加したうつ病に対する精神療法のシンポジウムで最後に質問した人のようにアリピプラゾールによる増強療法の最新の知見はどうなのか,どの抗うつ薬を組み合わせれば最強なのか?と聞いてくる人がいる。新しいルール探しに精神科医はこだわることを止められない。50代以上の精神科医なら,昔の三環系抗うつ薬の方が新規抗うつ薬よりも効果が高いと知っているが,そのような古いルールには誰も見向きもしない。私たち,精神科医たちは最新の知見,最新のエビデンスというルールに支配されてしまい,実際のアウトカムという目の前にある現実から目を背けているように見える。
3. 過去から今を見る
1980年代のうつ病の論文を今,引き出して読むと,当時からいかに私たちが進歩していないかがわかる。当時の方が良かったことがある。先々には解決するだろうという明るい雰囲気があった。融道男先生の「うつ病の病因-最近のトピックス」(2)を読むと,つぎつぎ明らかになる神経生化学研究の知見や新規抗うつ薬によって,いずれは本誌で取り上げたような問題が解決するだろうという明るい見通しがうかがえる。
今,そう思う人がいるだろうか?軽症例のうつ病の治療は新薬によって解決するだろうか?アクセプタンス・コミットメントセラピーやマインドフルネスのような第三世代の認知行動療法(6)によって解決するだろうか?臨床と治験,認知行動療法の普及に直接関わってきた原井の立場からはNoと答えるしかない。もし,はっきり,Yesと答え,それをサポートできるエビデンス,コホート研究による疫学的研究を出せる人がいたら私は引き下がろう。
エビデンスはなくても,1980年当時のように曖昧に,あるいは先々には解決するだろうと答える人がいるかもしれない。その人の言うとおりに,本当に実効性のある進歩が得られたとしよう。そのような進歩が日本全国に普及し,うつ病で受診する患者数が減少するという時代が来たとしよう。しかし,それでは困る人たちが出てくる。雨後の筍のように増えた駅前ビル診療所はどうやって経営をするのだろう?精神科病院は統合失調症患者の減少を認知症患者の増加で補うことができた。うつ病患者の減少を駅前ビル診はどうやって補うのだろう?今,児童思春期を専門にしている診療所はどこも2,3ヶ月以上の予約待ちがある。うつ病患者の減少を児童思春期の患者の増加で補うのだろうか?
本誌,「精神科治療学」を中井久夫先生たちが創刊し,当時の研修医仲間の皆が購読したのも,雑誌の主要なテーマが治療論であり,他の雑誌のように病因論や診断論ではなかったからだろう。中井久夫先生が1980年当時,注目されていたのは統合失調症の病因ではなく,寛解過程に注目したからだ。同じように軽症例のうつ病の治療はどうあるべきか?という問いに答えが与えられないならば,問いそのものを変えなければならない。30年近くたって解決つかない問いがあるのは,答えられない人のせいではなく,問いのせいである。
II. 今,学びつつある精神科医はどうしているのか?
1. 30代の精神科医の疑問
原井は50代の精神科医である。精神科医の仕事が曖昧なまま,この先にも進歩がないことで原井自身は困らない。私が仕事を失うことはおそらくない。しかし,患者自身はもちろん,これから精神科医としてのキャリアを積もうとしている若い人たちは困るだろう。100万人のうつ病の患者さんたちが精神科医を見離したら,彼らは仕事を失ってしまう。うつ病の患者数が10万人で精神科医のまたごく一部だけが診ていた時代は終わっている。精神科以外の医師も,また心理士などもうつ病の自分たちのターゲットと見なしている。
30代の精神科医はどう思っているのだろうか?その1人である橋本に疑問点を考えてもらった。
うつ病学会のうつ病治療ガイドラインが出た。読んで疑問が増えた。結局,薬物療法が必要なのか不要なのかはっきりしない。軽症例では積極的には使わない方向で行こうという方針はあるが,消極的になりすぎるのもよくないし、暫定的判断で使ってよいとも書いてある。結局それで、いままでの処方パターンを変える人がいるのか。結論はそもそも無理なのかもしれないが,そうならば今回のこのガイドラインは何のためなのか?と感じてしまう。
2. 個人的オピニオンに基づいて答えるならば
これは治療ガイドラインは役に立つのかという問題と、その内容についての問題に分けて考えることができる。まず,ガイドラインについて考えてみよう。ガイドラインを出せば,医者の処方がその通りになるか,というと、そのようなエビデンスはない。ガイドラインを出したからと言ってその国の医療内容が良くなったとか、それこそDSMがでたからといって、精神科医の診断に妥当性や信頼性が出たというエビデンスは原井の知る限りない。ガイドラインをネットで公開すれば,人の行動が変わる,とくに多剤併用のような問題処方をしている人が変わると期待する人は,教科書を渡せば学生は勉強するはずだと思っている教師と似ている。
内容を見てみる。“1 把握すべき情報”は見残しがないよう全てを網羅しようとしている。発達障害には特に詳しい。しかし,このガイドラインは治療方法の選択のガイドラインなのだから,詳しく調べることが治療方法の選択につながるべきだが,そんなことは書いていない。詳しく調べて結果がでても治療法は同じならば調べる意味がないし,必要が生じたときに後から調べても良いはずだ。一方,抜けているものがある。解離性障害(転換性障害)について触れていない。虚偽性障害もない。二次的を含む疾病利得のことを考えなくて良いと思っている臨床家として楽天的すぎる。初診時から自立支援や障害者手帳,診断書を要求してくる患者は珍しくない。そして,決定的に欠けているものが,過去の病歴・反応性である。ライフチャートとよぶ過去の病相を年表のようにしたものが必要だ。これがなければ大うつ病性障害反復性か単一か,双極性障害か,急速交代型かわからないし,この区別は治療方法の選択につながる。
例えば季節性感情障害には高照度光療法を検討するとある。その通りだと思う。特異的な治療法だ(3)。害も少ない。残念なことに,どうやって季節性感情障害をアセスメントするのか書いていない。ライフチャートを2,3年分つくればわかることなのだ。
過去の病歴も医療使用歴まで全てまっさら,病前性格も社会適応も悪くない,発症がこの1ヶ月ぐらい前からという患者,初治療の単一エピソードの患者で,いわばメンタルヘルス・バージンの患者ならば,このガイドラインが役立ちそうだ。しかし,このようなメンタルヘルス・バージンの患者を診たときに,ガイドラインが必要だと思う精神科医はどのくらいいるのだろうか?詳しく調べるまでもなく笠原の小精神療法で十分だ,無理して抗うつ薬を使わなくても,睡眠薬を飲んで寝ればそのうち良くなるだろう,と考えるのが普通の医者だろう。
3. エビデンスに基づいて答えるならば
では軽症うつ病に対する薬物療法について,原井以外の他の医師ならどう答えるだろうか?一時,精神科医の間で,NICE Guideline(7)が,初診のうつ病患者に対して,すぐに抗うつ薬を出すのではなく,最初は経過観察することを勧めていることが話題になった。この件について,EBMに詳しい同僚と意見をやりとりしたことがある。その一部を以下に示す。
原井:軽症うつ病に対する薬物療法について,NICE Guideline(7)では,
Antidepressants are not recommended for the initial treatment of mild depression, because the risk-benefit ratio is poor.
としているので,これに従うことにしています。
某医師:NICE Guidelineでは,Guided Self-Help以外の根拠はすべてC,つまりexpert opinionsになっています。それでもこれに従うのですか?一方,major depressionのmildなものなら薬物療法の効果がランダム化比較試験(RCT)で示されています(8)。これによると、minor depressionについてはwatchful waitingで良いと思います。軽症うつ病がminor depressionを指すのなら、NICEの言うとおりだと思いますが、「うつ病」と書くのだから、mild major depressionのことを言っているのですよね?
1980年代から進歩したもので有意義なものを1つ取り上げろと言われれば,原井が最初に考えるのがEBMである。エビデンスがあるから,私は行動療法や動機づけ面接をするようになった。RCTに基づいて治療法を選ぶことに賛成である。一方,彼からのメールには戸惑った。一つにはNICE Guidelineを作成したチームが彼以上にEBMについて詳しい人たちだと思うからである。二つ目には実際に治験で40例以上のうつ病の患者にプラセボを投与し,その結果を知っているからである。メタアナリシスでは抗うつ薬はプラセボより効果が優るのだろう。40例では少なすぎて差がつかないのだろう。しかし,プラセボは40例だけでもはっきりと抗うつ薬よりも副作用が少ない。三つ目にはRCTは効果がプラセボと同等であるという帰無仮説を否定しただけであって,抗うつ薬を投与すべきだとガイドラインに明記し,うつ病の治療に当たる医師全員がそれに服従することで,実際のうつ病に悩む患者が減る,ということまで証明したわけではない。NICEのチームは,現在,入手可能な最強のエビデンスをもってしても,軽症うつ病患者の全員に抗うつ薬を服用させろと医師全体に命じるようにガイドラインには書くには至らない,と判断したのである。世の中で数多く行われたRCT全体を見渡してみよう。帰無仮説が否定できなかった,すなわちプラセボなどの比較対象との間に差を証明できなかった治療法のほうがはるかに多いのである。認知療法の用語でいえば,EBMは否定的認知のスキーマに骨の髄まで染まっている。1回のRCTで肯定的な結果が出ても信じない。追試を繰り返して,肯定的な結果が続き,そして比較対象との差が十分に大きくなければ,その治療法に根拠があるとみなさない。
4. クリニック経営に基づいて答えるならば
原井と橋本は年代は違うが,共通点がある。2人とも医療法人が経営するクリニックの勤務医である。今日のクリニックと1980年代の大学病院とは目標が違う。1980年代の医療機関,とくに公的なものには経済観念がなかった。国公立精神病院は平気で赤字を垂れ流していた。今のクリニックの経営者には集患・増患という観念がある。経営者は患者が気軽に受診できるよう,クリニックの場所や入り口の雰囲気に気を使う。ホームページの整備は当然である。来てくれた患者さんに対しては,不安や嫌な気持ちが来たその日から楽になり,眠れるようになり,患者が次もまた薬を求めてクリニックに来てくれるように処方を工夫する。初診の患者を増やし,再来の患者はできるだけ長く続けてくるようにさせることが集患・増患なのである。。薬を貰うために長年,通い続けてくれる患者は担当医が退職などで変わっても続けて来てくれる,クリニックの経営を支えてくれる。「いわば固定資産だ,大事にしなさい」と教えてくれたクリニック経営者がいた。精神科に限らず何科のクリニックであっても,あるいは全ての客商売において集客(患)は必須であり,常連客(患者)こそが収益を磐石にしてくれる。景気変動や病名の流行り廃りとは無関係になるからである。
こう考えれば,初診で来たうつ病の患者に対して経過観察をするなどありえない。うつ病と抗うつ薬を知らない大人の日本人はまずいない。自らうつ病ではないかと思ってクリニックに来た患者に「確かにうつ病ですかが,軽いから」と言って薬を出さないのは,患者を驚かせるだけだろう。せめて今晩だけでも楽に眠りたい,という患者は他のクリニックに移ってしまいそうだ。最初から抗うつ薬,スルピリドなどの抗精神病薬の少量,抗不安薬2種(長時間型の定期服用と短時間型の頓服)の4種をセット処方にして出してしまう手を勧めてくれたのが先ほどの経営者である。これが“固定資産”を増やすのに役立つと経験でわかっているのだろう。
III. 薬だけではない
本論のテーマは薬物療法だった。認知行動療法は大丈夫なのだろうか?実は認知行動療法も同じ問題を抱えている。抗うつ薬と同等の効果がある,だから効果のエビデンスがあるというのが常套句である。しかし,抗うつ薬自身がプラセボとそれほど差が無い,副作用やコストなどの点も考えに入れれば,軽症うつ病の場合には抗うつ薬の効果は必ず処方すべきと言えるほどではない。20歳以下に関しては効果を示すエビデンスがないと添付文書に明記されるまでになった。プラセボとそれほど差が無いとされる治療法と同等ということは,認知療法もプラセボとそれほど差が無いということだ。認知療法には薬のような副作用はないから,効果の点で優越性がなくても,臨床的な有用性があると主張する人がいるだろう。しかし,よく考えてほしい。プラセボは治療マニュアルを作成したり,治療者をトレーニングしたりする必要がない。1回30分かけて,毎週受診,10回続けるという患者の手間暇もかからない。そして,全国どこでも使える。認知療法ができる精神科医が不足しているのは確かにそうだろう。では,プラセボ治療ができる精神科医は不足しているのだろうか?国立菊池病院で原井は多くのプラセボ対照ランダム化比較試験を治験責任医師として手がけたが,プラセボを出す医者を探すのには困らなかった。そして,キーオープンの後,それぞれの医師の治療成績を振り返ると,男性医師が女性を担当した場合,女性医師が男性を担当した場合にそれぞれプラセボ反応が高かったが,それ以外には医師個々人での差は無かった。プラセボ治療は医師間のバラツキが小さいのである。
プラセボは診断基準やエビデンス,認知モデルに基づかない。何故効くのか?と効いても答えがないからプラセボと呼ぶ。私たちは逆に考える必要がある。診断がより正確になり,判断を頼るべきエビデンスが増え,認知モデルや治療法が増えること自体に問題があるのだろう。しかし,良い進歩を問題視し,他の方法は?と問う人はまだいないようだ。
DSEn診断をしていた精神科医たちは,言い方を変えれば,こんな風に診断していたともいえる。DとS,Eはそれぞれ抗うつ薬と抗精神病薬,抗てんかん薬が必要な患者である。神経症のnは,抗不安薬だけで良く,それも一時的使用に限り,ずっと続けて精神科に来るべき患者ではない。そもそも大学病院の医師で患者の数を増やしたいと願う者はいない。DSEn診断はどの薬を誰が飲むべきかだけを決めるための診断だと言える。患者は少ない方が早く仕事が終わるし,診断は少ない方が迷いも少ない。そしてそんな精神科医ばかりだったせいで,地域におけるうつ病の患者数が少なく,難治性も少なくて済んでいたのかもしれない。
1980年代,日本の精神医療は入院治療に偏り,欧米と比べて地域精神医療が貧弱過ぎると非難された。クリニックの開設は入院中心から外来・地域精神医療中心への転機になるはずだった。デイケアなども備えて,慢性精神障害者に対するノーマライゼイションを目指しているはずだった。結果的には,今起こっていることは,“メンヘラー”という新しい慢性患者を作っているだけのように見える。治療し,成功するとは結果として減患することである。減患という言葉はまだ日本語にない。
文献
- Association AP. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III). 3rd ed. Washington DC, USA: American Psychiatric Press; 1980.
- 古川壽亮. エビデンス精神医療. 東京: 医学書院; 2000. p. 6.
- 厚生労働省:傷病別年次推移表 [Internet]. [cited 2013 May 27]. Available from: http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/02syoubyo/1-1b4.html
- Murphy GE, Simons AD, Wetzel RD, Lustman PJ. Cognitive therapy and pharmacotherapy. Singly and together in the treatment of depression. Archives of general psychiatry [Internet]. 1984 Jan [cited 2013 May 24];41(1):33–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6691783
- 気分障害の治療ガイドライン作成委員会日本うつ病学会. 日本うつ病学会治療ガイドライン うつ病性障害2012 Ver.1. 2012;1–61.
- 原井宏明. アクセプタンス・コミットメント・セラピー(ACT)の利点は何か. 精神医学(0488-1281). 2012. p. 352–6.
- Middleton H, Shaw I, Hull S, Feder G. NICE guidelines for the management of depression. Bmj. British Medical Journal Publishing Group; 2005;330(7486):267.
- Paykel ES, Hollyman JA, Freeling P, Sedgwick P. Predictors of therapeutic benefit from amitriptyline in mild depression: a general practice placebo-controlled trial. Journal of affective disorders [Internet]. [cited 2013 May 26];14(1):83–95. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2963054